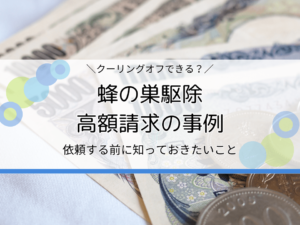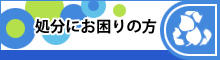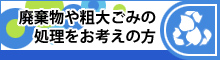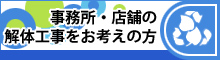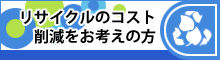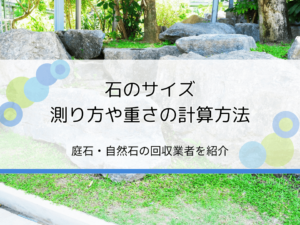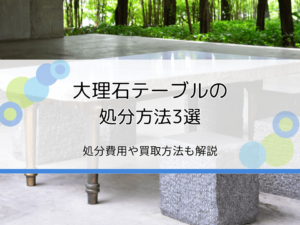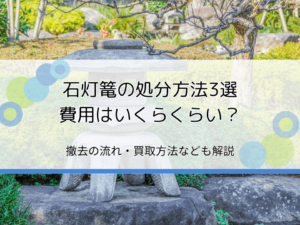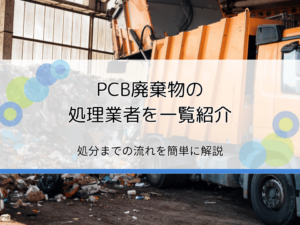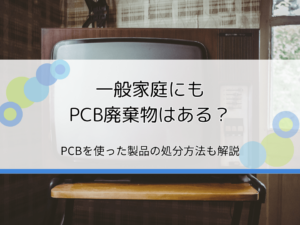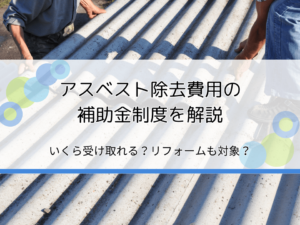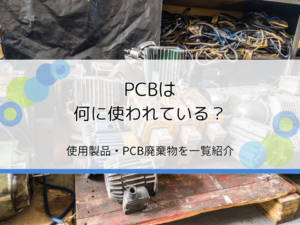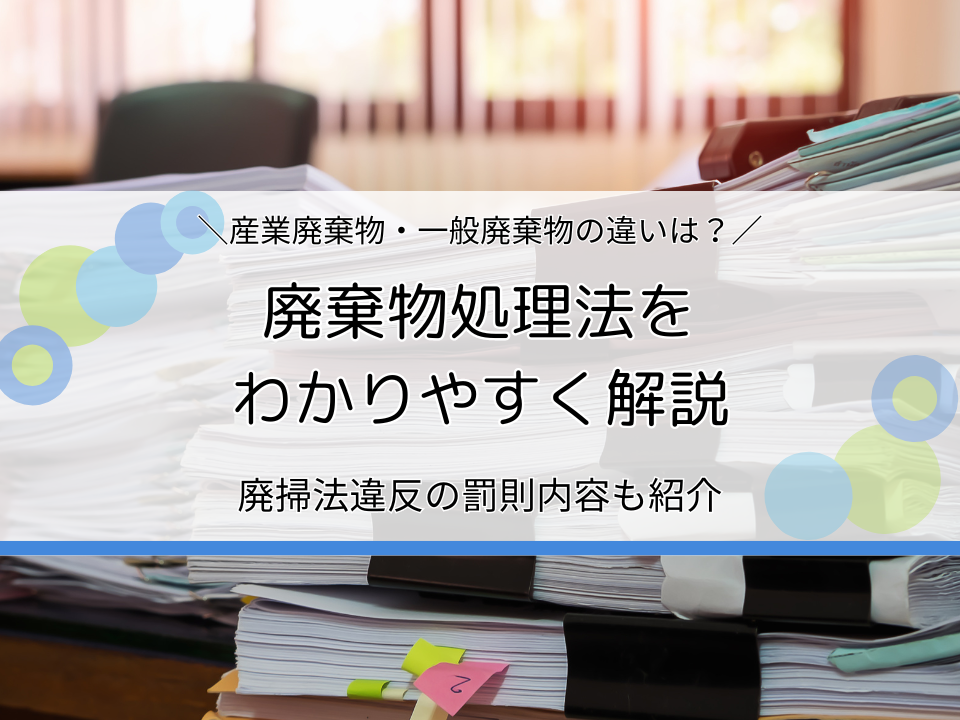
この記事では様々な事業を営む上で知っておきたい「廃棄物処理法(廃掃法)」をわかりやすく解説していきます。
廃棄物処理法とは、ゴミを捨てる際のルールをまとめた法律です。当然、ルール(=法律)を守らなかった場合は個人・法人問わず罰則を受けることになります。
廃棄物処理法を理解しないまま事業をおこなっていると、知らないうちに法律を破ることになりかねません。
また、ゴミの処分を専門業者に依頼した場合でも最終的な責任は「ゴミを出した事業者」にあるため、回収業者・処理業者の選び方も重要となってきます。
ここでは廃棄物処理法における産業廃棄物と一般廃棄物の違いや定義、種類といった部分も解説していますので、ぜひ最後までご覧になっていってください。
目次
廃棄物処理法をわかりやすく解説|産業廃棄物・一般廃棄物の違いや定義について
廃棄物処理法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のことです。
ゴミを出す個人や法人(=ゴミの排出事業者)とゴミを回収処分する業者(=ゴミの処理業者)の両方に関わる法律となります。
廃棄物処理法では、排出されるゴミを産業廃棄物・一般廃棄物の2つに分けています。時代に合わせて法律の内容は改正されていますが、まずは基本的な部分から見ていきましょう。
廃棄物処理法施行令(廃掃法)とは?
廃棄物処理法施行令は「廃掃法」とも略される法律です。国土の保全や公衆衛生を守るために、1971年9月(昭和46年)に制定されました。
ゴミは適切な形で処分しないと土壌の汚染や疫病の蔓延に繋がってしまいます。私たちの健康や国土を守るためにも廃棄物処理法の遵守は大切ということです。
廃棄物処理法は第一章~第五章まであり、ゴミの出し方や処分方法に関するルールが定められています。
特にゴミの分別・収集・運搬・保管・処分といった処理の工程は厳格に決まっているため、すべての事業者はこれを守らなければなりません。
なお、ゴミを出す側は「排出事業者」ゴミを処分する側は「処理事業者」と呼ばれていて、大半の排出事業者は処理事業者にゴミの処分を委託することになります。
しかし、この際には「排出事業者責任」というものが生じるため、ゴミが適切に処理されたかどうかを最後まで確認しなければいけません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条第1項において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされており、また、同法第11条第1項において、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています(排出事業者責任)。
引用:排出事業者責任の徹底について|環境省HP
廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。廃棄物処理法第12条第7項では、事業者は、産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。
簡単に言えば、自分が適切に分別して出したゴミでも処理事業者が不適切な形でゴミを処分した場合には「自分の責任になる」ということです。
そのため、ゴミの処理事業者を選ぶときには信頼性や実績を自分でチェックしなければなりません。
また、事業ゴミの中には大きく分けて「産業廃棄物」「一般廃棄物」の2つがあり、正しく分別することも必要です。
廃掃法における産業廃棄物・一般廃棄物の定義
産業廃棄物と一般廃棄物の定義は以下の通りです。
- 産業廃棄物:事業に伴い生じたゴミのうち、法律で定められている20種類の廃棄物
- 一般廃棄物:事業に伴い生じた産業廃棄物以外のゴミ
それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物には以下2つの種類があります。
| 廃掃法におけるゴミの区分 | 内容 |
|---|---|
| 産業廃棄物 | 法令で定められた20種類の廃棄物 |
| 特別管理産業廃棄物 | 強い毒性や爆発の恐れがある有害な産業廃棄物 |
産業廃棄物に指定されているのは廃酸・廃アルカリ・金属くず・がれき類・動物の糞尿などの20種類です。
このうち、規定の数値から外れる廃酸・廃アルカリなどの廃棄物、感染や爆発の危険性がある廃棄物が特別管理産業廃棄物として扱われます。
特別管理産業廃棄物を捨てる際は、同廃棄物の収集運搬・処分許可を得ている業者に依頼しなければなりません。(一般の産業廃棄物処分業者には任せられないということ)
なお、産業廃棄物に分類されるゴミに関して、詳しい情報は以下の記事を参考にしてください。
一般廃棄物の種類
一般廃棄物には以下3つの種類があります。
| 廃掃法におけるゴミの区分 | 内容 |
|---|---|
| 事業系一般廃棄物 | 産業廃棄物以外の事業系ゴミ |
| 特別管理一般廃棄物 | 事業系一般廃棄物のうち有害性が高いゴミなど |
| 家庭廃棄物(家庭ゴミ) | 一般家庭から排出される日常的なゴミ |
事業系一般廃棄物は家庭ゴミと同じようには捨てられません。そのため、基本的には「一般廃棄物収集運搬業者」に処理を依頼します。
一部、飲食店から出るゴミなどは自治体から指定されたゴミ券を購入し、ゴミ袋に貼ることで捨てられます。(もしくは契約しているテナントや施設内のゴミ集積場に捨てる)
特別管理一般廃棄物とは「産業廃棄物以外で感染や爆発などの恐れがあるゴミ」のことです。
一例としてはエアコンや電子レンジなどに含まれる「PCB使用の部品」や「廃水銀」が挙げられます。
上記以外で一般家庭から出るゴミは家庭廃棄物扱いとなります。
覚えておきたい廃棄物処理法の改正内容
廃棄物処理法は時代と共に改正を繰り返しています。ここでは、近年に改正された内容で覚えておきたいものを以下にまとめました。
- マニフェストの虚偽記載等に関する罰則強化
- 一定の基準を満たす事業者に対する電子マニフェスト発行の義務化
マニフェストとは「産業廃棄物管理票」のことです。紙タイプと電子タイプの2種類があります。
産業廃棄物を排出する事業者はマニフェストを発行し、処理事業者・最終処分業者に渡さなければなりません。

「排出された産業廃棄物がどこにあるのか」「最終的にどこで処分されたのか」を知るために発行されるのがマニフェスト(産業廃棄物管理票)です。
簡単に言えば不法投棄を防ぐための措置となりますが、2018年以降は廃棄物処理法が改正され、マニフェストに関する内容がより厳しくなりました。
廃棄物処理法へのよくある質問にわかりやすく回答
ここからは廃棄物に処理法に関するよくある質問に回答していきます。
ネット上で多くの方が疑問に感じている部分を分かりやすくまとめましたので、ぜひご覧ください。
廃棄物処理法第7条の内容は?
廃棄物処理法第7条の内容は以下の通りです。
第七条
引用:廃棄物の処理及び清掃に関する法律|e-GOV法令検索
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
第7条は「一般廃棄物処理業」に関する内容となっています。
分かりやすく言いますと、各自治体(市区町村など)から許可を受けていなければ一般廃棄物の収集はできないということです。
産業廃棄物だけでなく、一般廃棄物の処分に関しても「認可済みの業者」を選ぶ必要があります。
廃棄物処理法第12条第7項とは?
廃棄物処理法第12条第7項の内容は以下の通りです。
事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
引用:廃棄物の処理及び清掃に関する法律|e-GOV法令検索
こちらは先ほども解説した「排出事業者責任」に関する項目です。
ゴミを排出する事業者は最終処分までチェックを怠ってはいけません。また、こうしたチェックのために利用されているのがマニフェスト(産業廃棄物管理票)となります。
廃棄物とごみの違いは?
ゴミを含めて「不要となったもの」「処分するもの」が廃棄物です。
しかし、事業者からすれば不要かつ処分対象となっていても、まだ使えるものはあります。
対してゴミは「単体では無価値なもの」「そのままでは利用できないもの」と解釈されます。
廃棄物の中にはゴミ以外のものもあるが、基本的にゴミは廃棄物になるといったイメージです。
とはいえ、近年は単体で無価値なゴミも「できる限りリサイクルする」といった方針や政策が取られています。
廃棄物処理法の罰則は?
廃棄物処理法に違反した場合の罰則は、その違犯内容によって異なります。
一例として代表的な違反・罰則を以下にまとめましたので、参考にしてみてください。
| 廃棄物処理法違反の罰則 | 違犯内容 |
|---|---|
| ・5年以下の懲役 ・もしくは1,000万円以下の罰金 ・または上記の両方 | ・無許可営業 ※許可を得ずに一般廃棄物/産業廃棄物の収集・運搬・処分作業をおこなった場合 ・営業許可の不正取得および更新 ・事業停止命令違反 など |
| ・3年以下の懲役 ・もしくは300万円以下の罰金 ・または上記の両方 | ・委託基準違反 ・再委託禁止違反 ※ゴミの排出事業者が、一般廃棄物/産業廃棄物等の処理の基準に反して、運搬や処分を委託した場合 など |
| ・1年以下の懲役 ・もしくは100万円以下の罰金 | ・排出者管理票交付義務違反および記載義務違反 ・排出者管理表の虚偽記載 ※適切な形でマニフェストを発行しなかった場合、またはウソの内容を記載した場合 など |
ご覧のように廃掃法の対象となる違反は多いので、あらかじめ内容を確認しておきましょう。
廃棄物を処分する際の適切な方法は?
「各自治体から正当な営業許可を得ていて、なおかつ実績がある専門業者に任せる」というのがもっとも安心かつ適切な処分方法と言えます。
なお、産業廃棄物収集運搬業の許可を得ていない業者に産廃物の処分を委託することはできません。
産業廃棄物を含め事業系のゴミを排出する際は「産業廃棄物収集運搬業許可」を得ている業者に依頼を出し、産廃物と事業系一般廃棄物の分別をしてもらった上で回収もお願いしましょう。
廃棄物処理法に則ってゴミを処分するなら信太商店がおすすめ
事業に伴い生じた産業廃棄物や一般廃棄物、家庭ゴミの処分を検討している方は信太商店までご連絡ください。
当社は様々な廃棄物に対応した認可済みの専門業者です。「特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可」も得ているため、通常では処分が困難な廃棄物でも回収できます。
信太商店の会社情報・営業許可
| 事業者名 | 信太商店 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2-5-6(本社) 東京都渋谷区笹塚3-44-8(笹塚営業所) |
| 対応エリア | 対応エリア一覧 東京、千葉、埼玉、神奈川、栃木、茨城、群馬、静岡 ※その他のエリアも対応可能な場合がございますのでお問い合わせください |
| 設立年月日 | 平成22年(2010年)4月23日 |
| 主な事業内容 | ・産業廃棄物収集運搬業 ・一般貨物自動車運送業 ・沈没船引き揚げおよび解体処分等 ・樹木の伐採および木材販売事業 ・リサイクル事業 ・蜂の巣駆除および回収 |
| 取引先・一例 | NHK、防衛省、ヤマト運輸株式会社など多数 |
| 許可・免許等 | 【産業廃棄物収集運搬業】 ・東京都許可 第1300154938号 ・千葉県許可 第1200154938号 ・埼玉県許可 第1100154938号 ・神奈川県許可 第1400154938号 ・群馬県許可 第01000154938号 ・栃木県許可 第00900154938号 ・茨城県許可 第008011154938号 ・静岡県許可 第02201154938号 【特別管理産業廃棄物収集運搬業許可】 ・東京都 ・千葉県 ・神奈川県指令 資循第6002号 【ほか許可・免許等】 ・古物商 ・一般貨物自動車運送業 ・解体工事業 ・移動式クレーン免許/小型移動式クレーン 2級建築施工管理技士/フォークリフト 酸素欠乏危険作業主任者など |
| 営業時間 | 受付時間 8:00~20:00 業務時間 24時間対応 |
| 公式URL | https://www.shida-eco.com/ |
当社は東京都渋谷区に本社を構える産業廃棄物収集運搬業者です。沈没船や大型樹木といった特殊な廃棄物の回収もおこなっています。
なお、上記の通り関東一円の営業許可を取得しているため、安心してゴミの回収をご依頼いただけます。
信太商店の作業実績・料金
以下では当社の作業実績や料金をご紹介しています。産業廃棄物や一般廃棄物の処分を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
ご覧のように金庫の回収・大型機械の撤去・樹木の伐採など、信太商店は様々なご依頼に対応しています。
信太商店の問い合わせフォーム・連絡先
各種廃棄物の回収依頼は以下の問い合わせフォームや連絡先をご活用ください。
| 電話番号 | フリーダイヤル:0120-937-277 笹塚営業所:03-6381-6141 |
|---|---|
| 問い合わせフォーム | https://www.shida-eco.com/inquiry-for-business |
| メールアドレス | shida@shida-eco.com |
当社では「すぐに回収してもらいたい」「時間を指定したい」といったご要望にも応えています。もちろんお見積りは完全に無料で、現地調査が必要な場合でも見積もり費用を加算いたしません。
そのほか、他社と料金を比較したいといった場合もお気軽にご相談ください。
まとめ
事業系のゴミを処分する上で知っておきたい「廃棄物処理法(廃掃法)」を分かりやすく解説してきました。
- 廃棄物は大きく分けて「産業廃棄物」「一般廃棄物」の2種類
- 最終責任はゴミの排出事業者にある
- 正当な処理事業者を選ぶことが大切
産業廃棄物・一般廃棄物ともに処分を委託する場合は、各自治体から営業許可を得ている正当な処理事業者を選びましょう。
関東近郊であれば信太商店が責任をもって回収に伺いますので、ぜひご利用ください。